はじめに
2020年1月に Windows 7 のサポートが終了しましたが、その後も多くの企業・自治体が業務の都合で移行できず、Extended Security Updates(ESU) を利用しました。
そして 2025年10月、Windows 10 のサポート終了に伴い ESU の利用が控えています。
👉 本記事では、Windows 7 ESU の実際の利用事例を振り返りつつ、Windows 10 ESU 活用のヒントを整理します。
なお、具体的な登録手順を知りたい方は 👉 Windows 10 ESU 登録方法の徹底ガイド もあわせてご覧ください。
Windows 7 ESU の仕組みと現実
提供期間
- 2020年1月〜2023年1月までの3年間
- 毎年更新契約が必要で、年ごとに料金が増額
価格(法人向け)
- 初年度:1台あたり約50ドル
- 2年目:倍額の100ドル
- 3年目:さらに倍額の200ドル
👉 最終的に1台あたり合計350ドルという高コストになりました。
運用上の実情
- 自治体や金融機関:業務アプリの互換性問題で移行が遅れ、ESUを採用
- 中小企業:コスト負担が重く、最終的に Windows 10 への更新を決断
- 一般ユーザー:個人向け提供がなく、法人契約経由での導入例もありました
Windows 7 ESU で得られた教訓
- 「延命」であって「解決」ではない
→ 3年間の延長は時間稼ぎに過ぎず、最終的に移行は必須。 - コスト増が現実的な負担
→ 年ごとに倍額となり、「初年度は安い」と思って契約したが、長期的には高額化。 - 互換性問題の根深さ
→ 特に独自アプリや古い周辺機器の存在が、移行を阻んだ最大要因。 - セキュリティ以外は更新されない
→ 新機能や改善は提供されず、利便性は旧環境のまま据え置き。
Windows 10 ESU への適用と相違点
共通点
- 提供期間:最大3年間
- 更新内容:セキュリティパッチのみ
- 最終的に「移行は避けられない」
相違点(Windows 10 の新要素)
- 個人向け ESU 登録が可能
→ Microsoft アカウント経由で簡単に登録できる(有料/無料オプションあり) - 法人向けも同様に年ごと倍額
→ Windows 7 と同じくコストは上昇傾向 - Windows 365 やクラウドPCでの提供
→ Windows 11 への移行を促す「代替策」も用意されている
シナリオ別:Windows 10 ユーザーの選択肢
1. 個人ユーザー
- 短期延命派:年額30ドルで 1〜2年だけ延命し、その間にPC買い替え
- 長期利用派:Rewardsや同期特典を活用し、無料枠を狙ってできる限り引き延ばす
- リスク:最終的には2028年で完全終了
2. 法人ユーザー
- 選択肢A:ESUを購入 → 業務アプリの対応完了まで時間を稼ぐ
- 選択肢B:クラウドPCへ移行 → Windows 365 を利用して段階的に Windows 11 へ移行
- 選択肢C:一斉更新 → PCリプレースをまとめて実施し、長期運用コストを抑制
まとめ:過去を踏まえて「移行戦略」を前倒しに
- Windows 7 の ESU は「コスト増」「移行遅れ」という現実を残しました。
- Windows 10 も同じ轍を踏む可能性が高く、ESUは最終手段と位置付けるのが現実的です。
- 2025年のいまから、Windows 11 への移行計画を立てることが最良のリスクヘッジになります。


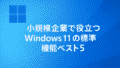
コメント